1.1 データベース 改めて勉強
- 2025.04.10
- データベースとデータモデル
- DB, 基礎

データベーススペシャリスト試験に向けて基礎から学習を始めようと考えているが、この年になって正直しんどい。。。だが将来、教育といったお仕事に興味あるので、まずは以下の教科書を選び一読してみて基礎から学習を始めようと思います。
今後、学習した内容を理解を深めるために当サイトにアウトプットしく。
1.1 データベースとは
- 長期間にわたって必要とする情報のかたまり
- DBMS(DataBase Management System:データベース管理システム)によって管理されるデータの集合体

DBMSの機能
- データベースの論理構造を定義する機能でデータ定義言語(DDL:Data Definition Language)
- データベースの内容を問い合わせたり、更新したりする機能でデータ操作言語(DML:Data Manipulation Language)
- 大量データの格納管理機能
- 多くのデータベースユーザーの同時アクセスにおいて、データに矛盾が生じないようにする機能で同時実行制御機能
データベースの役割
当初は、階層型データベース、ネットワーク型データベース、構造型データベースが中心であった。
データベースを考えると、トランザクション処理を中心とした基幹系のデータベース、日々の発生あるいは変化するデータを扱う事が中心と考える。
この日々のデータを履歴データとして、そして時系列をキーとして蓄積たものを情報系のデータベース。これをデータ倉庫という意味からデータウェアハウスという。
データの独立性
データベースはオフコン時代のファイルシステムと違い、データの整合性を保つこと、そしてオフコン時代には密にプログラムとデータがつながっていたが、プログラムからデータを独立して管理する事によりデータベースという分野というか考え方が必要になったと思う。
これをプログラムからデータを独立性するという。独立して管理する事でプログラムの変更がデータベースに影響しない、またはデータベースの変更がプログラムに影響しない疎結合な関係になり、汎用性がアップする。
データベースが独立性をアップするためには、データ自体を管理するデータが必要。これをシステムカタログ、データディクショナリまたはメタデータ(データのデータという意味)といい、データや定義などを管理するためのデータが必要となった。
-
前の記事

プロジェクトマネジメント 仕事で意識してること 2025.04.10
-
次の記事
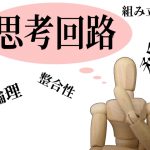
3.2整合性管理 2025.04.10